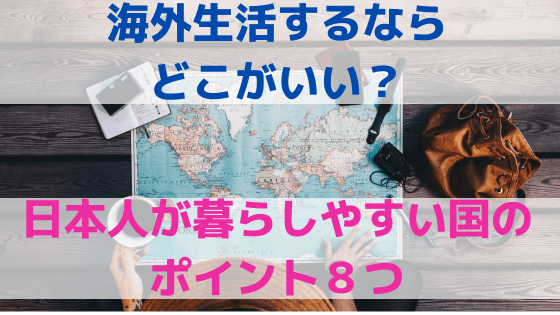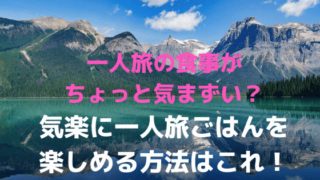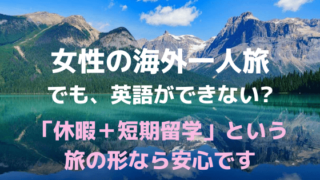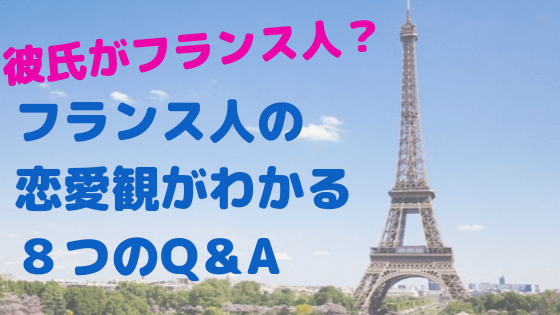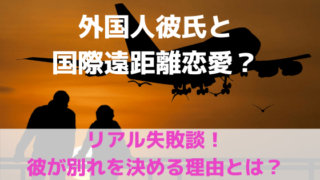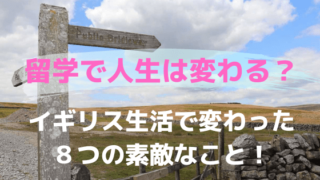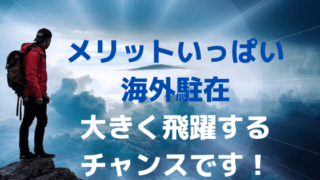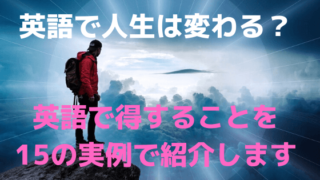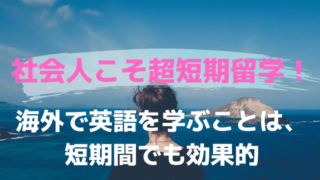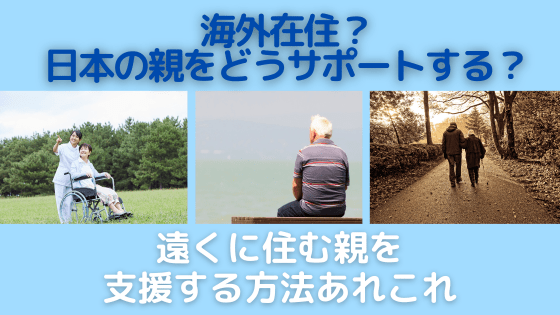
 国際結婚で海外在住です。
国際結婚で海外在住です。
日本の両親が高齢になってきて、とても心配。
海外に住む自分ができる親へのサポートについて情報が欲しい。
こんにちは、まのん(@ManonYoshino)です。
海外生活が長くなってくると、自分も歳をとりますが、それ以上に気になるのは日本に住む親のこと。
40代、50代の在仏女性の共通の話題といえば、子供の教育に自分の健康、そして日本の親への心配です。現実には、日本とフランスを行き来して介護している人もいますし、もう親御さんを亡くされて実家の管理や兄弟の介護に入られている人もいます。
親が高齢になって困った時にどうしよう
そんな不安を抱えていませんか?海外に住んでいるから自分には何もできないのでは、と思い悩んでいるかもしれませんね。
「何もできない…」なんて、そんなことはありません。
遠く離れていても親をサポートする方法はいろいろありますよ。
この記事では、
海外から日本の高齢の親をどうサポートするのか
サポートが必要になる具体的なシーンと対策
海外からの高齢者サポートの難しい点
についてみていきます。
漠然と不安に思っていらっしゃる方のために、自分の経験も合わせてご案内していきますのでぜひご覧ください!
目次
海外から日本に住む高齢の親をサポートできる?

最初にざっくりと結論を言ってしまいます。
海外から日本に住む高齢の親を、いろいろな方法で生活支援することは可能です。
インターネットが当たり前、誰でもがスマホを持ち、IoTと呼ばれる「モノのインターネット」が普段の生活に入ってきている今なら、可能性はさらに広がっていると言えるでしょう。
日本の親の遠距離支援は海外在住者が共通に持つ悩み
海外に住みながら高齢になった日本の親の生活をどうサポートできるのか…、この悩みを持つ人は少なくありません。
今、実際になんらかの方法で頑張っている人も多いでしょう。
きっと海外移住を決めた時点では、自分も、そして日本のご両親もまだまだ若く「老後の不安なんてまだ先のこと」だったと思います。
少なくとも、この記事を書いている筆者はそうでした。
晩婚・高齢出産だったにもかかわらず、「親はまだまだ元気で暮らしていく」とのんきなものでした。当の両親も、自分たちの健康と長寿には全く疑いを抱いていませんでした。
でも、「後期高齢者」という年代に差し掛かった頃から、日本の両親は怪我をしたり、病気になったりして弱り始めたのです。
我が家は、認知症などで長期の介護が必要な状況にはならず、急に病気で亡くなりました。それでも、遠距離からの支援方法を試行錯誤し始めて、なかなかうまくいかずに悩みもしました。
自分の周りの在仏日本人でも、高齢になった日本の親御さんの看病に帰省したり、体調を心配したりしている人がたくさんいます。それぞれ悩み、工夫しているようです。
▼ 海外生活が長くなるにつれて、気になり始めるのが日本の両親のこと。遠く離れているからこその不安に、海外在住者ができる親の老後の寄り添い方を考えます。
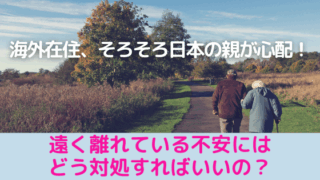
海外から高齢の日本の親をサポートできる?
先に書いたように、遠く離れていても日本の親のためにできることはけっこうあります。
以前は、
✔︎ ビデオ通話で頻繁に連絡を取る
✔︎ 日本在住の兄弟姉妹と連携体制を組む
✔︎ 一時帰国時に介護保険の事務手続きなどをする
といった、どちらかといえば「そっとケアする」感じの方法が主流だったと思います。
でも、今やスマホやタブレット、IoT機器で日本ともっとアクティブに繋がれる時代。海外にいながらにして、日本に暮らす親御さんの日々の様子を見守ることさえ可能なんですね。
そこに「安否確認訪問」や「訪問医療・介護」「生活支援」をしてくれる事業者との連携を加えれば、さらに心強いですよね。
海外から日本の親をサポートする方法

ここからは日本の親を海外からどうサポートできるのか、具体的にみていきましょう。
- 買い物や家事などの日常生活
- 急病や怪我をした時
- 入院など緊急時
- 介護が必要な時
海外在住者が手伝える日常生活支援
日常生活で高齢者が困りがちなことには、大きく分けると次の3つがあるでしょう。
買い物
家事
移動
買い物支援
日常生活に必要な食料品や日用品など、買いたくても買いに行けない買い物弱者の高齢者が増えています。
足腰が弱ってしまった、重い荷物を運べない、スーパーや商店が近所にない…。
郊外型の大型店舗が主流になってきて、街中の個人商店がどんどん減っています。「高齢者は運転免許を返上しろ」と言いながら、日常生活には車が必要不可欠なエリアも多いです。
高齢者が買い物弱者になる…、これは田舎に限ったことではなく、都会でも同様です。徒歩圏内にスーパーやドラッグストアなどがないところもありますよね。
また、徒歩での買い物は、若い人ならなんとかなるでしょうが、体力が落ちてきた高齢者には大変な重労働。
離れて暮らす子供世代としては、親が買い物に不自由しているのを見るのは切ないことです。なんとかならないものか、と思いますよね。
一般的に買い物弱者の高齢者をサポートする方法は
✔︎ 移動販売を利用してもらう
✔︎ ネットスーパーを利用してもらう、利用をサポートする
✔︎ 会員制の食品・日用品デリバリーを利用してもらう
などが考えられます。
移動販売車
各地方自治体でも、この問題は真剣に捉えていて、自治体がスーパーとタイアップして「移動販売者」を運営しているところもあります。親御さんがお住まいの自治体のホームページをチェックしたり直接問い合わせてみるといいでしょう。
ネットスーパー・デリバリーサービス
また、ネットスーパーや会員制のデリバリーサービス(生協など)の利用も考えてみてはいかがでしょうか。
高齢の方が、こうした新しい「買い物方法」に慣れるには、少し時間がかかります。親御さんが元気でいるうちに、できるだけ早めにスタートして、「注文して配達してもらう」「ネットで注文する」という買い物方法に慣れてもらうよう支援していくことがポイントです!
ネットスーパー・デリバリーサービスを支援する方法
「うちの親はネットが使えない」「物忘れが多く、すぐに使い方がわからなくなる」という場合は、曜日を決めて親に連絡し、代理発注するという方法もあります。
我が家はこの方法で支援しました。毎週決まった日に子供たちが交代で実家に連絡し、代理発注。
これなら海外からでもサポートできますし、国内の兄弟姉妹と協力体制を組んで交代ですることもできるでしょう。
ネットスーパー・デリバリーサービス利用の問題点
ただ、やはり「習慣」にするにはかなりの努力が必要です。長年、自分でスーパーに出向き、食材を手に取って選んできた人たちが、ある日を境に自由に買い物できなくなる…というのは相当な苦痛のようでした。
「まとめて発注するから欲しいもの教えて」という買い物方法に、急にシフトするのは大変なことなのです。
ネットショッピングやまとめ買いは、ぜひご両親が元気なうちに一緒にスタートしておくことをおすすめします。
家事サポート
買い物のほかにも掃除や調理など、生活していくにはいろいろな家事がついてまわりますよね。これも、体が自由に利かなくなったり、病気になったりすると、高齢者が自力でこなすのは困難になってきます。
そこで、家事をどうやってサポートしていくか…ということが課題になってきますよね。
4つのステップで考えていきます。
① 自治体の地域包括支援センターに相談し、介護認定を受ける
⬇︎ ⬇︎ ⬇︎
② 介護認定を受けて、介護レベルに合わせてヘルパーを頼む
⬇︎ ⬇︎ ⬇︎
③ 介護保険ないでまかなえない部分や、不定期なサポートには民間サービスの利用も考える
⬇︎ ⬇︎ ⬇︎
④ 食事に関しては、宅配食のサービス利用も考える
① 地域包括支援センターに相談、② 介護レベルに合わせてサービスを設定
介護認定を受けると、介護レベルに合わせてヘルパーを頼むことができます。掃除や洗濯、食事の支度や介助などをお願いすることも可能ですし、買い物をお願いすることもできます。
詳細については、まずは自治体の地域包括支援センターに相談。「ケアマネージャー」をアサインしてもらえば、さまざまな手配やアドバイスを受けられますよ。
③ 民間サービス利用を考える
介護保険内ではまかないきれない部分や、不定期なサポートには、保険外の支援を行う事業者も。料金はサービス内容によってさまざまですが、いざという時には頼りになる存在と言えるでしょう。
または家事代行サービス業者に依頼して、定期的にヘルパーさんに来てもらって手伝ってもらうという方法もありますよね。
④ 食のサービス利用を考える
食事に関していえば、宅配食もさまざまなサービスがあり、こちらの利用もかんがえてみる価値がありそうです。
高齢者向けの減塩食や、食べやすく調理したお弁当など、各事業者とも工夫を凝らしたメニューが…。なかには、宅配食&安否確認を同時に行っている事業者もあります。
上記の多くの部分は、海外にいてもネットやメールで調べたり相談したりが可能!
移動の問題
高齢者世帯の困りごとの一つ、「移動」。
「高齢者は免許返納しろ」というのは簡単ですが、買い物だけでなく「通院」の足の確保も大きな問題点なんです。
自分の両親の晩年を見ていて痛感したことですが、本当に「通院」が頻繁。月曜日は歯科医院、火曜日は内科のクリニック、金曜日は怪我の治療で外科医院…、みたいにほぼしょっちゅう違う医療機関にお世話になってました。
足を怪我して運転できない期間は、たまたま自分が一時帰国中で運転手できましたが…。
「運転が危うくなってきて、しかもこんなに通院が多くて、これは困った事態だな」と思いました。
地方の自治体が運営している相乗りタクシーやコミュニティバスがあれば、利用を考えてみましょう。
「いざという時」が来る前に、一時帰国時に親御さんと一緒に利用してみるといいかと思います。
繰り返しますが、「慣れ」はとても大切なのです!
あとは、タクシーですが、頻繁かつ距離も長い移動なので高額になりますよね。それでも安心にはかえられないかもしれません。
もうひとつ、保険外ヘルパーさんの外出・通院付き添いサービスを利用するという方法もあります。
ふだんの安否確認
いつもなら家にいる時間なのに、電話に出てくれない…!
携帯にかけても全然つながらない…!
離れて暮らす親と連絡が取れない時、とても不安になりますよね。
でも今では、IoT(モノのインターネット)が汎用化されたおかげで、海外からでも日本の両親の安否確認が可能になっています。できることが増えました!
若い元気な人なら、旅行に出ているのかなとか、出張中かなとか、さほど大ごとには感じませんが、高齢者世帯では急な病気や怪我なども考えてしまいます。
様子がわからないだけに、最悪の事態を心配してしまったり…。
うちでもよくありました(たまたま電話をかけた日に、珍しく両親二人そろって遠方の親戚のお見舞いに行っていたということも)。頻繁にビデオ通話で様子を確認してはいましたが、相手が不在ではどうにもなりませんよね。
こういう不安を解消してくれるのが、スマートホームを使う見守りです。
ソニーがMANOMA(マノマ)という防犯・見守りシステムを提供しているのはご存知ですか? 日本の実家に設置したIoT機器をスマホアプリと連携させるサービスです。
【 Sony MANOMA 親の見守りサービス 】

高齢の親が心配、という人におすすめなのがSonyが提供するMANOMA(マノマ)の「親の見守りセット」。
MANOMAを導入するとできることをいくつかご紹介しましょう。
① カメラとセンサーで、遠く離れた親の生活が見える!
✔︎ 開閉センサーを冷蔵庫や玄関、トイレのドアなどに設置。開閉をセンサーが察知すると、登録してあるスマホに通知が送られる仕組み。離れた高齢の親の安否を確認できる。
✔︎ 室内カメラで親の今現在の状況を知ることができる。アプリを通してコミュニケーションをとることもできる(わざわざ電話をかける必要がない)。
✔︎ 室内カメラの人感センサーが人の動きを察知し録画。転倒や怪我など、万一の事故のときにも状況を知ることができる。
② 機器を追加すれば、エアコンの温湿度設定や玄関の施錠などの生活サポートも遠隔地から可能。
③ セコムとタイアップした「駆けつけサービス」を付加すれば緊急時にはセコムが駆けつけてくれる。
④ 離れていても、家族最大7名で同時に見守りができるので、兄弟姉妹それぞれが実家の状況を把握することが可能です。
⑤ 取り付け工事が不要で、置くだけ・貼るだけで設置できる。
⑥ 初期設定の代行から使用中の困りごとまでサポートが充実している。実家にネット環境がない場合は、Wi-Fiも同時に設置してもらえる。
さらに詳しく知りたい方は、公式サイトへ>> 離れて住む親を見守るなら、MANOMA(マノマ)
Sony のMANOMA以外にも、SIM カードを搭載した家電製品の使用がアプリを通して通知される、というものもあります。
「室内カメラ」の設置に抵抗感を持つ人もいるので、そういうご家庭には、「そっと異常なしが確認できる」システムの使用がいいかもしれません。
例えば、SIMを搭載できる電球というのがあります。これを、トイレの電球に取り付け、24時間点灯がないと異常としてお知らせが届くといったもの。
他にも「🔍見守り家電」で検索すると、いろいろなオプションが見つかるはずです。
緊急時(入院など)の対応
日本に住む親が急な病気や怪我で入院する場合…。突然の連絡、慌ててしまいますよね。いったい、どう対応すれば良いのでしょうか。
まず、日本にすぐに対応できる親族がいるかどうかで、その後の対応が変わってきます。
親が一人暮らしという場合、日本に兄弟姉妹がいれば連絡を取り合って、協力体制を組むこともできます。
対応を頼める人がいない場合は、最初に病院側から正確な情報を得ることが重要でしょう。オンラインで相談や手続きが可能かどうかも確認ポイントです。
また、入院や手術には病院指定の「準備品」が必要。親族ですぐに対応できないときは、親が親しくしている親戚やお友達にお願いするという方法もあるでしょう。
いずれにしても、自分以外に親族がいない場合は、できるだけ早い段階で一時帰国が必要かと思います。病院によっては、院内のソーシャルワーカーとリモートで相談ができるかもしれません。
親が高齢になってきたら、普段の帰国時に「近くに住む親戚」「ご近所さん」「地域の民生委員」とは連絡先を交換しておくことをおすすめします。
入院が長期化しそうな場合、退院後も生活支援が必要な場合、早い段階で実家のある自治体の「地域包括支援センター」に相談してみましょう。こちらも病院内のソーシャルワーカーがアドバイスをしてくれるはずです。
介護が必要になった時の対応
もし、親が要介護になったら…。
多くの子世代が不安に思うことですよね。
海外在住の自分が全部やることには少し無理があります。でも、高齢化が進む日本では、さまざまな支援の仕組みができているので、情報を集めてみてください。
そして、「地域包括支援センター」から担当のケアマネジャーさんがつけば、高齢者支援に必要なことをアドバイス・手配してもらえます。
介護保険でお願いできるサービスもありますし、保険外のさまざまな支援を提供する事業者もたくさんあるので、うまく組み合わせてサポートしていけるのではないでしょうか。
▼ 海外在住者は、「もし親の介護が必要になったら…」という不安と、どう向き合ったらいいのでしょうか。いざというときに慌てないために、備えておきたいポイントを考えてみました。
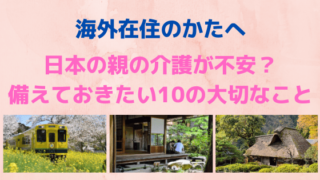
海外からサポートする際に注意すること

親が高齢で身の回りのことが不自由になってきた、病気や怪我で入院、または介護が必要…となったとき。
これはかなりのストレスになります。意外なところで本音が出てきていざこざが起きることも実はよくある話。後々のトラブルに発展しないよう、注意しておくポイントがあります。
兄弟姉妹間で話し合う
「カリフォルニアから来た娘」という言葉、聞いたことがありますか?
入院や介護などが必要な高齢者のために、身近な親族でいろいろ手配したところに後からやってきた遠方の子供が口を出す…という困ったシチュエーションのことだそうで…。
兄弟姉妹が協力して親の生活をサポートする、これが理想ですよね。
でも、実際はそんなにうまくいかないことだってあります。
離れて暮らす親が弱ってきた、介護が必要だ、という状況になると関係者はみんなそれなりに不安だしピリピリします。
金銭的な問題もあるでしょう。
兄弟姉妹、それぞれに配偶者がいれば、そちらからの口出しもあるでしょう。そして、それぞれ守っていかなければならない自分たちの暮らしもあります。
上手に連携を取れるよう、日頃から連絡を取り合うことが大切だと思います。そして、「同じ家で育った」とはいえ大人同士なので、お互いを尊重して感謝し合うこと。これ、すごくすごく大切です!
親の意向を確認する
支援を受ける側の親の意向の確認も大切な作業なんです。ここが一筋縄でいかず、先に進めないというご家庭は多いよう。
介護認定なんて受けたくない
入院はもういや、自宅に戻りたい
他人が家に入るのがイヤ、ヘルパーいらない
デイケアは行きたくない
施設に入るのは絶対イヤ。一人で自分の家で暮らす
例えば見守りサービスのモニター設置も「見張られているようでイヤだ」と頑なに拒否される親御さんもいるそうです(気持ちはすごくわかります)。
元気な時は「老後だの介護だの縁起でもない」と言われ、いざ本当に介護が必要になったら本人の意思確認ができなくなっていた…というご家庭の話も聞きます。
とてもセンシティブな話ですが、できるだけ親が元気でいるうちに「歳をとったら…」「もし介護が必要になったら」という話し合いをしておくといいですよね。
事業者のサービス内容を確認する
見守りサービスや、宅配食、家事代行など、さまざまな支援サービスを利用するなら、契約前にその内容をよくチェックします。
- 金銭面:初期費用と継続してかかる費用に、追加でかかる可能性のある費用など、具体的にいくら必要なのか
- サービス面:受けられるサービスの内容は?
途中で変更や解約が可能なのかどうかも、はっきり知っておくと安心ですよね。
実際の契約時には、しっかりと契約内容を確認したいもの。あとあとのトラブルを未然に防ぐ意味でも、内容はよく把握しましょう。
海外からでは難しいことも実はある

ここまで、海外在住でも、高齢になった日本の親をいろいろな形でサポートできるとお伝えしてきました。海外からでも、ネット環境さえ整えば、さまざまなことをリモートでできるようになりました。
ただ、なかなか遠隔地からではできないことも実はあるかと思います。
難しいことの例
ざっと考えるに、次にあげるものは家族や親族が直接出向かないと難しいことが多いようです。
✔︎ 病院の付き添い・入院や手術の手続きと準備
✔︎ 在宅介護時の環境整備
✔︎ 行政・金融機関の手続き
何が難しいのか、どう対応すれば良いのか、それぞれ見ていきましょう。
病院の付き添いや入院時の手続きと準備
遠隔地からでは、当然、通院時の付き添いはできないですし、入院や手術となった時の提出書類に直接署名することもできません。
病状をしっかり知るためには、親の通院時に同行して主治医に直接話を聞く必要がありますよね。病院側からも、「ご家族と一緒にお話しさせてください」「ご家族の方の同意が必要です」と言われることが多々あるかと思います。
入院や手術でも、身元保証人は入院申込書への署名捺印、手術や輸血などの同意書への署名捺印を求められるでしょう。
これら「直接話を聞く」「署名捺印」が必要な時にはどのようにしたらよいのでしょうか。
海外在住者がどう対応しているかというと、
日本在住のきょうだいが対応してくれている
近くに住む叔父が対応してくれている
母の友人が対応してくれている
など、やはり日本に住んでいる人にお願いしているケースがほとんど。
ただ、「身元保証人」は金銭の支払い保証も含まれるので、親族以外には頼みにくいと感じる人も…。困った時は、病院のソーシャルワーカーに相談してみるのがよいようです。
可能であれば、日本に短期間でも帰国できるといいですよね。親御さんも安心されるでしょうし、ご自分でも親御さんの様子や病院の環境がわかるのでその後の対応も考えやすくなります。
帰国できれば、担当医から直接話が聞けますし、ソーシャルワーカーやケアマネージャーとも詳しい話し合いができるでしょう。
在宅介護時の環境整備
自宅で暮らし続けたい、でも暮らしていくには何らかの生活支援が必要という高齢者には、介護保険制度で受けられるさまざまなサービスあります。
自治体の地域包括支援センターに相談すると、ケアマネジャーのアサインから介護認定の手続きなど進めてくれるでしょう。
ただ、在宅介護において必要なものなどの整備は「ご家族でお願いします」と言われることが多いかもしれません。
兄弟姉妹に頼れない場合、自分が帰国して対応しないといけない場面も出てくるようです。
行政手続き・金融機関の手続き
例えば戸籍謄本や納税関係の証明書を取得したい時…。誰かが自治体の役所に出向く必要がありますよね。
戸籍謄本や住民票などは、本人でなくとも委任状を用意すれば取得できますが、物理的に取りにいかないといけないのがネック。
また、金融機関の手続きも、「印鑑をなくした」「定期預金を解約して普通預金に移したい」などというとき、自分の口座ではないためオンライン手続きは不可。
誰かが物理的に役所に出向かないとできない手続きのほか、本人同行でないとどうにもならない手続きもあります。こちらも、手続きに行ける親族がいない場合は、自分が帰国して対応する必要があるかもしれません。
単身の高齢者が増えている今、「高齢者終身サポート」事業者が増えているとのこと。日常の生活支援から、入院時の身元保証、そして死後事務までを家族に代わって行ってくれる民間のサービスです。
もちろん料金はかかりますし、いろいろなサービスを付加すればするほど高額になります。ですが、死後の葬儀から公共料金や携帯電話、クレジットカードの解約などさまざまな最後の事務処理までを請け負ってくれるサービスがあると思うと少し心強いですよね。
まとめ
海外在住者ができる日本の高齢の親へのサポートについて考えました。
日本の親とは遠く離れている、時差がある、どうしよう…と不安に感じている人も多いことでしょう。
でも、さまざまなツールやサービスがどんどん登場しているので、遠い国からでも支援できることがきっとあるはず。
いろいろ調べてみて、一時帰国の際には親御さんとも話されてみてはいかがでしょうか。